厳しい暑さが続く8月は、東洋医学では「長夏」にあたり、湿気と暑さが身体に影響を与えやすい時期と考えられています。この時期は、特に**脾(ひ)**の働きが弱まりやすく、食欲不振や胃もたれ、だるさなどの症状が出やすくなります。また、夏の強い日差しや高温は「暑邪(しょじゃ)」として身体に侵入し、熱中症や頭痛、倦怠感を引き起こすこともあります。
8月の養生ポイント
- 脾をいたわる食事: 冷たいものの摂りすぎは控え、温かく消化の良いものを意識しましょう。カボチャ、トウモロコシ、枝豆など、旬の野菜は脾の働きを助けます。また、ハトムギや緑豆もおすすめです。
- 適度な運動と休養: 汗をかきすぎない程度のウォーキングやストレッチで身体を動かし、適度な休養も大切です。睡眠不足は脾の負担になるので、規則正しい生活を心がけましょう。
- 湿邪・暑邪対策: 湿度が高いと体内に「湿邪」が、高温だと「暑邪」が溜まりやすくなります。除湿器を活用したり、風通しを良くして快適な環境を保ちましょう。外出時は日傘や帽子で直射日光を避け、こまめな水分補給を忘れずに。
鍼灸治療で夏の不調をケア
東洋医学では、夏の不調は「気」や「津液」の消耗、そして「湿邪」や「暑邪」の停滞が原因と考えます。鍼灸治療では、これらのバランスを整えることで、身体が本来持つ回復力を高めます。
例えば、胃腸の働きをサポートするツボや、全身の巡りを良くするツボ、そして熱を冷ますツボを刺激することで、夏の疲れやだるさを和らげ、食欲増進にも繋がります。定期的な鍼灸治療は、夏の不調を乗り切り、健やかな毎日を送るためのサポートとなります。
今年の夏も、東洋医学の知恵と鍼灸治療で、心身ともに快適に過ごしましょう。何か気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
#鍼灸 #東洋医学をもっと身近に #東洋医学 #ヨガ #養生 #はりきゅう #温活 #肩こり #腰痛 #頭痛 #むくみ #消化器症状 #倦怠感 #小顔 #7月 #8月#暑邪 #湿邪
#土浦市 #守谷市 #常総市 #牛久市 #つくばみらい市 #取手市
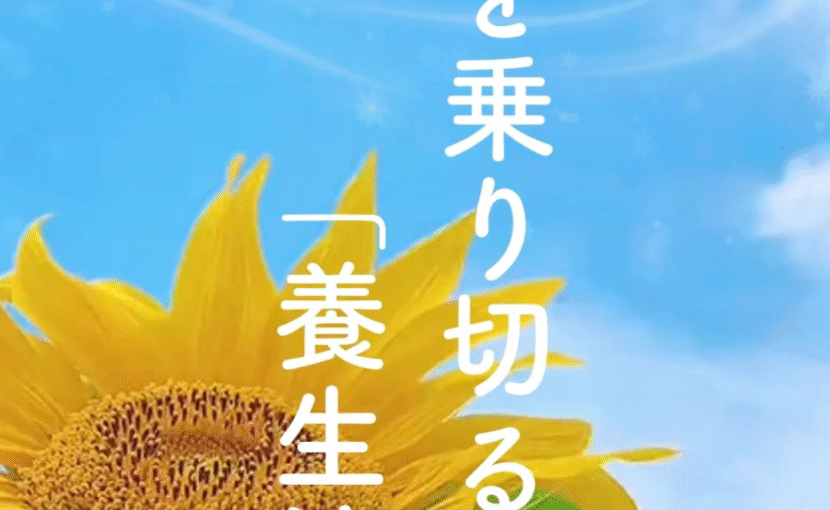
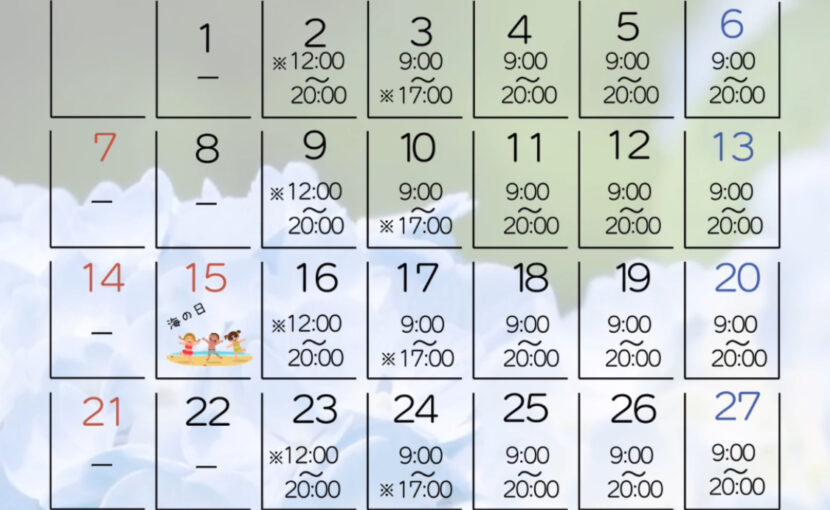


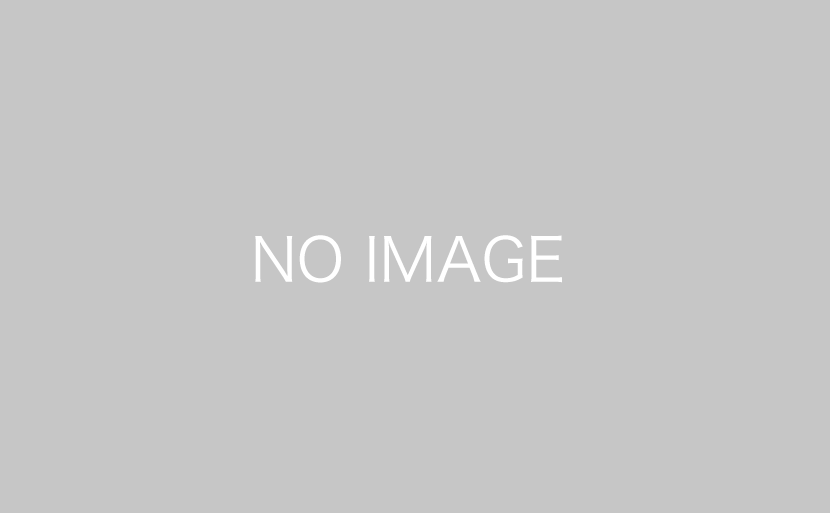
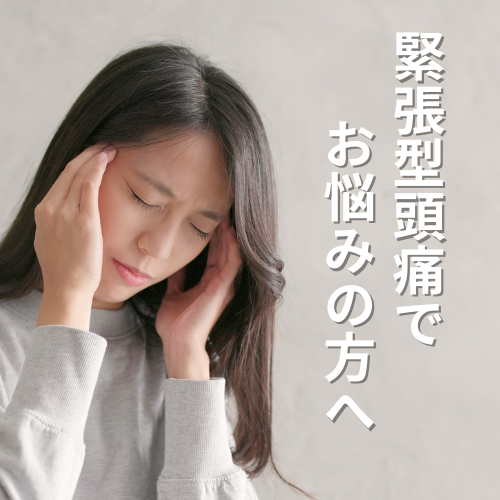

この記事へのコメントはありません。